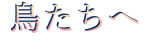キジバトの鳴き声はどのように聞こえますか?と先生に尋ねられて、他の鳥のさえずりを再現するよりも何倍も難しいと気づいた。私は歌った、「ポポッポ ポッーポー」って聞こえます。よく図鑑に書き表されているのは「デデーポッポー」であるから、私の歌は他の人の聞こえ方とずれている。すると先生は、「私には、パフアニューギニアと聞こえます」と言った。鳥の鳴き声を言葉に置き換えることを、聞きなしと言うが、キジバトの聞きなしに国名が出てくることはそうそうない。鳥の鳴き声の再現性の難しさと面白さに感動した一場面だった。
木枯らしが吹くのが遅れた長い夏だったから、街にはキジバトの鳴き声がそこらじゅうで聞こえた。よく耳を澄ますと、彼らの鳴き方に違いがあることに気づく。かなりの個体差がある。あるものはゆっくりと鳴き、あるものは早く鳴く。テンポの良いものもいたし、音痴に思えるくらい安定しない鳴き方をするものもいた。さえずりをするオスの鳥は、その鳴き声でメスにアピールし、つがいを獲得するわけだから、上手なものがメスにモテる。うちの前に巣をつくり、毎日のように電線の上でないていたキジバトは、非常にゆったりと安定した鳴き方をしていた。そして一回の鳴き方が長く、朝から夕方までよく鳴きに来ていた。その豊かな鳴き方と存在から、私は彼を「長老」と名付けた。実際の年齢はもちろんわからないが、人生経験があるような、そんな鳴き声だったからだ。キジバトのさえずりは、つがいの獲得のためだけではなく、縄張りの宣言の意味もある。埼玉県の住宅地の、大通りを一本入った家の並ぶ通りを陣地と決めた彼は、他のハトが鳴いているのを見逃さない。ある日、長老とは明らかに違う鳴き方をするキジバトが、数軒先の家の前の電線上に鳴きにやってきた。負けじと長老はうちの前の電線上で鳴く。しばらくすると、別のハトは一本奥の通りに飛んで行った。そんな出来事も、「長老」と名付けた理由の一つだった。
そんな長老は、夏の終わりごろにつがいを獲得した。キジバトはつがいを形成してから、子育てをする巣をつくる。うちの前にあるオリーブの木には、もともと別のハトがつくった古巣があり、長老はメスと出会う前にその巣の存在を確認していた。さ らに補強するために長老はせっせと枝を運んでいた。私はメスとふたりで巣の中に入っていたりする場面を見かけた。ただ、その巣で子育てをするかどうかはメスが決めるらしい。何度かふたりがくつろぐ姿を見たのだが、十日ほど経ったころ、まったく来なくなってしまったのだ。長老も、そのパートナーも、他のハトでさえも!静かになった家の前に私は悲しみを覚え、彼らの元気を願っていた。おそらくほかの場所に決めたのだろう。私が執拗に観察していたのが気に食わなかったのかもしれない。
それからさらに十日ほど経って、あきらかに長老と思える鳴き声が聞こえてきた。キジバトはメスもオスも協力して抱卵や子育てを行うが、その合間で彼は自分の大切な縄張りのパトロールをしに来たのだろう。久しぶりに聞いた彼の豊かな鳴き声は、私に向けられているような気がした。別の場所で確かに生きているよと言わんばかりに。
夏が過ぎてようやく寒くなると、キジバトの声は全く聞こえなくなってしまった。代わりにヒヨドリの大群が一斉に鳴き叫びはじめた。だが、キジバトたちを見なくなったのではない。街を散歩していると、草地の中を採食したり、木の実をむしって食べたり、木から木へと飛び移ったり、木の中でまどろむキジバトを見る。夏の間はあんなにも我を主張していたのにも関わらず、寒くなるにつれ、彼らは鳴かずに、採食に集中して冬を越す。
ある暖かい十月の日に、一度だけ長老がやってきたことがある。そして短い時間ではあったが、またあの豊かな声を披露してくれた。彼はパートナーと、またはひとりで、この近くで確実に生活をしている。声では判断ができるのに、彼の姿かたちは残念ながら特徴的なものはなく、(ほかの個体より少し大きいような気がするのだが、)ほかのキジバトと並べられたら、鳴かない限り当てることは難しいだろう。知らぬうちに、私は長老とすれ違っているかもしれない。見かけるすべてを長老と思い、今日も元気に、確かに生きてくれよと思う 。
戻る